59秒の真実
K.G.ファイターズ 攻撃コーディネーター
小野 宏
法政・池場の逆転TD
 |
 |
自陣32ヤードから始まった法政の攻撃は、じわじわと進みながら関学陣に入り込もうとしていた。ベンチに座る攻撃の選手達は落ち着かない表情だった。声の限り、守備を応援したい。ここで止めてくれれば、そのまま勝てる。しかし、法政もこのまま終わりはしまい。次に攻撃権が回ってくる可能性を考えて、心の準備をしなければ。……
 中途半端な気持ちのままでは、もし万が一、逆転されて攻撃権が回ってきたときに選手はあわててしまう。何か具体的な指示をしておきたい。揺れ動く心の中で、私は次のシリーズのことを考えようとしていた。このまま法政にタッチダウンされれば、時間はほとんど残されていないだろう。パス中心となることは敵も分かっている。頭の中で整理されたことは二つしかなかった。
中途半端な気持ちのままでは、もし万が一、逆転されて攻撃権が回ってきたときに選手はあわててしまう。何か具体的な指示をしておきたい。揺れ動く心の中で、私は次のシリーズのことを考えようとしていた。このまま法政にタッチダウンされれば、時間はほとんど残されていないだろう。パス中心となることは敵も分かっている。頭の中で整理されたことは二つしかなかった。
ひとつは、試合を通じてQBにかかっている守備ラインのラッシュの圧力をどうかわすか。特に左のDE木下をどうやって封じるかということ。頭に浮かんだのは、この試合でも何回かコールした「ダッシュ」だった。QBがいったんまっすぐにドロップバックして守備ラインを内側に引き付けておいてから、狭いサイドの外側にロールアウトするパスプレー。守備ラインはいったんラッシュしてから、方向を180度以上変えて追いかけ直さなければならないので、QBは時間的な余裕ができる。レシーバーもその分だけ時間を使って長いルートが走れる。
 特にボールを右ハッシュに持ってきてコールしたい。ダッシュはいろいろなフォーメーションからできるが、今回は1バックから狭いサイドへの展開しか準備していなかった。左にTEをおいたフォーメーションから右でダッシュできれば、左の木下をTEとTでダブルチームし、しかも木下から離れていけるからだ。
特にボールを右ハッシュに持ってきてコールしたい。ダッシュはいろいろなフォーメーションからできるが、今回は1バックから狭いサイドへの展開しか準備していなかった。左にTEをおいたフォーメーションから右でダッシュできれば、左の木下をTEとTでダブルチームし、しかも木下から離れていけるからだ。
もう一つは、相手がロングパスを警戒してプリベントで深く守っていたとしても、一発長いパスを通すことがどうしても必要になるであろうこと。このことで頭に浮かんだのも、ダッシュだった。ダッシュから準備していたSEの「アウト&ゴー」。通常のドロップバックのパスに比べると、レシーバーがフェイクに費やせる時間がずっと長い。時間のないシチュエーションでは、相手もアウトが多くなることを知っている。もしCBが色気を出してアウトに反応してくれれば、そのままタッチダウンできる可能性も出てくる。法政はSEサイドは常にCBが一対一でマン・ツー・マン的についている。このプレーも同じく右ハッシュ。左ハッシュなら、俊足の選手が集まった法政の中でも最も足が速いと思われる左CB中村と勝負しなければならない。まだわずかに右のCBと勝負した方が可能性が高い。狙うならここしかない。ベンチに座って不安げに戦況を見つめる攻撃の選手たちを集めて言った。「もし次のシリーズが回ってきたら、ダッシュを2回使う。イメージを作っておけ」。
それ以上のことは考えられなかった。
騒然としたスタンドの空気に包まれる中で、法政はじわじわと進んでいた。そして、関学陣43ヤードで第3ダウン1ヤード。残りは1分14秒。法政にとってこの残り時間が十分とはいえなかった。タッチダウンでなければ逆転できないこと、そしてタイムアウトを使い切っていたことが、法政に極限まで重圧をかけていた。フィールドゴールでいいのと、タッチダウンを取らなければならないのとでは、2ミニッツ・オフェンスを考えるうえで雲泥の差がある。この場面、法政はタッチダウン(あるいは大きなゲイン)を狙ってくるはずだ。中央のフェイクを入れて一発ロングパスを投げるだろう。第1ダウンを取るには第4ダウンで勝負しても構わない。「ロングパスあるぞ」。守備のサインは分からなかったが、とっさにDBたちに向けてベンチから大声で叫んだ。鳥内監督も同じことを考えていたようで「投げてくるぞ」と声を上げた。
しかし、次の瞬間、ベンチもスタンドも凍りついた。素早い中央のフェイクからボールはRB池場にピッチされていた。パスを注意させた分だけDBの寄りが遅れたようにも感じがした。後悔をする間もなく、池場はDBの間を走り抜けていた。そのスピードからして、誰かが追いつく可能性がないことはすぐに分かった。
法政側の仮設スタンドが歓喜に埋まる中で、(後から考えればだが)法政ベンチはミスを犯した。タッチダウンの後のトライ・フォア・ポイントをキックしてしまったのだ。タッチダウンで5点差。この状況でキックを成功させて6点差にしても意味はない。通常であれば、2点コンバージョンを狙って7点差を目指すのだが、残り時間から考えて勝利をつかみ取ったと思ったのだろう。しかし、それが結果的に最後に思わぬ決着を生み出す伏線となった。
 |
 |
 |
 |
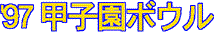

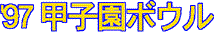



 中途半端な気持ちのままでは、もし万が一、逆転されて攻撃権が回ってきたときに選手はあわててしまう。何か具体的な指示をしておきたい。揺れ動く心の中で、私は次のシリーズのことを考えようとしていた。このまま法政にタッチダウンされれば、時間はほとんど残されていないだろう。パス中心となることは敵も分かっている。頭の中で整理されたことは二つしかなかった。
中途半端な気持ちのままでは、もし万が一、逆転されて攻撃権が回ってきたときに選手はあわててしまう。何か具体的な指示をしておきたい。揺れ動く心の中で、私は次のシリーズのことを考えようとしていた。このまま法政にタッチダウンされれば、時間はほとんど残されていないだろう。パス中心となることは敵も分かっている。頭の中で整理されたことは二つしかなかった。 特にボールを右ハッシュに持ってきてコールしたい。ダッシュはいろいろなフォーメーションからできるが、今回は1バックから狭いサイドへの展開しか準備していなかった。左にTEをおいたフォーメーションから右でダッシュできれば、左の木下をTEとTでダブルチームし、しかも木下から離れていけるからだ。
特にボールを右ハッシュに持ってきてコールしたい。ダッシュはいろいろなフォーメーションからできるが、今回は1バックから狭いサイドへの展開しか準備していなかった。左にTEをおいたフォーメーションから右でダッシュできれば、左の木下をTEとTでダブルチームし、しかも木下から離れていけるからだ。


