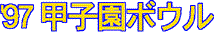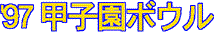59秒の真実
K.G.ファイターズ 攻撃コーディネーター
小野 宏
余話として
 |
|
いくつか、最後のシリーズのことについて付け加えたい。
不思議な予感、というのがあるものだ。甲子園ボウルの前日、練習の最後のハドルが解かれ、後は試合を待つだけという時になって、急に言いたいことが浮かんで攻撃の選手を集めた。私にとっての「関学のベストゲーム」は、1984年(昭和59年)の甲子園ボウルであることを伝えた。「あれほど、選手が最初から最後まで無心になって目の前のプレーに集中していたことはない。そういう試合を目指そう」とだけ言った。このゲームで、関学は残り1分37秒で8点差を追って自陣33ヤードから最後のシリーズを始め、残り4秒でタッチダウンを挙げ、2点コンバージョンも成功させて追いついた。同点ながら7年ぶりに日本一に返り咲いた試合だった。私は留年コーチだったが、甲子園では広瀬慶次郎ヘッドコーチが出すプレーコールの合間に自分でもコールを出していた記憶がある。ひどくその瞬間に集中しているため、点数も頭に入らず、何度も何度も試合中に「いま何点差や」と繰り返して聞いていたことを覚えている。そのことも選手に伝えた。純粋な「自由」だった、と思っている。その時にプレーしていた選手たちから感じた「人間の不思議な力」は、私を新聞記者からグラウンドに引き戻した大きな理由の一つでもあった。その最後のプレーは、QB縄船からWR菅野へのパスだった。メーンスタンドから向かって右側のエンドゾーンの左隅へ浮かしたパスは、いったんDBの手に収まりながらこぼれ落ち、そのボールを菅野が倒れながら取ったのだ。その時、今のQB高橋は小学校4年生、WR竹部は小学校3年生だった。直接は見なかっただろうが、彼らはビデオでこの試合を何度か見ている。そのことは、無意識のうちにあの場面でフィールドの選手に「勇気」を与えていたように思う。時をへてつながっているものがある、と思いながら、私は改めて歴史というものへの感慨に浸っている。
もう一つ、なんとなく書いておきたい風景がある。甲子園ボウルの2日前。甲子園球場での公式練習が終わり、そのグラウンドでそれぞれの選手が1時間ほど個別に練習できる時間があった。高橋はリラックスした時間の中で、竹部とあのエンドゾーンで(方向は試合と逆だったが)、ゴール前のフライの練習を繰り返していた。始めは二人のイメージが合わず、ちょっと不安を感じるような出来だったが、次第に二人の描いているボールの弧のイメージが一致していった。その合間。高橋は、前日の雨をまだ含んでいる緑色の芝生にうつ伏せになって目を閉じていた。夢に見た甲子園の感触を体に覚えこまそうとするかのように、いとおしそうに芝生を抱えるようにしてじっとしていた。竹部は「やるんなら早くやりましょうよ」と練習をせかしたが、高橋は「甲子園なんやから、寝なあかんやろ」と独り言のように言ったまま、起きない。竹部は、「そんなこと言って、他のやつが寝てたら怒るくせして」とあきれていた。なんとなく、彼らの心情が伝わってきたので、記しておきたくなった。
この文章を書いたのは、試合を終えて間もなく松田コーチに、「この試合のことは記録に残さなあかんで」と言われたからである。「その瞬間瞬間に誰がどんなことを感じ、どんな風になったのか。書いとけや」。記事ともエッセイともつかぬものになってしまったが、私自身がその瞬間ごとに(振り返ってではなく)感じたことに沿ってできるだけ忠実に書いたつもりだ。
それをインターネット上で公表するのは、チームの理念として「オープンであること」が最も大切である、と考えているからだ。これは、領家穣・前部長が部の50年史に記したことでもある。もちろん、すべてをオープンにできるわけではないので、戦術的にどうしても書けないところは伏せた。フットボール専門用語も実際にチームで使用しているものとは変えた。
もう一つの理由は、多くの人に最後のシリーズについてお褒めの言葉をいただいたが、特にフットボール関係者の場合は、最後から2プレー前の「アウト」に関心が集中していた。「残り20ヤード、残り8秒でアウトをコールしたのはすごかった。それしか得点の可能性はなかっただろう。あれこそ関学だ」。称賛の声が大きいほど、私は真実を伝えたい衝動にかられた。あれは私のコールではない。高橋が自分で判断したのだ。そのことの凄さを伝えたくて、それはつまりは今の学生フットボールの面白さの粋を伝えたくて、正月気分が抜けてから一気に書いた。これで、97年度のコーチとしての仕事に、ようやく区切りをつけることができる。
1998年1月15日